1. 学資保険って本当にお得?加入を迷っている人へ
「子どもの教育費のために学資保険に入ったほうがいいの?」
「銀行で貯金するよりお得なの?」
こんな疑問を持っている人は多いですよね。
学資保険に入るべきか迷う人が多いのは貯蓄の手段としてのメリット・デメリットが分かりにくいからです。
さらに、学資保険の特徴として、 子どもの教育資金を計画的に貯めるためですが、本当にお得なのかどうかは 「返戻率」や「インフレリスク」 を考えながら判断する必要があります。
結論としては、学資保険は昔ほどお得ではないのが現状です。
その背景として、今は低金利時代であり、返戻率が100%を切る商品もあります。
そのため、「将来の教育費をしっかり準備したい!」と思って加入したのに、実際に受け取れるお金が支払った金額より少ない というケースも珍しくありません。
加えて、最近の物価上昇を考えると、学資保険で貯めたお金の「価値」も将来的に目減りする可能性があります。
したがって、学資保険だけに頼るのではなく、他の方法を検討する必要があるかもしれません。
💡 まずは自分にとって「本当に必要なのか」を考える

学資保険に加入する前に、次のポイントを整理しましょう。
教育資金を☟
- 確実に貯められる仕組みが欲しい?
もし貯金が苦手なら、学資保険の「強制貯蓄」機能はメリットになる - 親に万が一のことがあった場合、教育資金の保証が必要?
親にもしものことがあった場合、支払いが免除され、満額受け取れるメリットがある
学資保険の積み立て以外の保障とは?
例えば、親が契約者として学資保険に加入している場合、
💡代替案としては、積立型の死亡保障を選択する方法もあります。例えば、学資保険ではなく、よりシンプルな積立型保険や生命保険を選ぶことで、教育資金に必要な金額を効率的に貯めつつ、死亡保障も確保できます。
つまり、「育英金がついているから」という理由だけで学資保険を選んでしまうのは、実は費用対効果が低い場合があるため、しっかりと自分のニーズに合わせたプランを選ぶことが大切です。
まとめ
このように、この保険は「強制貯蓄」としては便利だが、昔ほどお得ではない。
- 低金利で返戻率が100%を切ることもある(→詳しくは3章)
- インフレの影響で将来的に「お金」の価値が下がる可能性がある(→詳しくは4章)
- 親の万が一に備える「死亡保障」がついてるとコストがかかる点に注意
- 「学資保険だけ」に頼らず、他の方法と比較することが大切!
💡学資保険の目的は「教育資金を貯めること」強制的に貯めたいなら学資保険、柔軟に増やしたいなら投資や預金と組み合わせる選択肢を考えよう!
2. 学資保険の最大のメリットは「お祝い金」?本当にお得なのか?

学資保険の広告やパンフレットでは、「お祝い金が受け取れる!」と強調されていることが多いですよね。
でも、実はこの「お祝い金」こそが、学資保険の返戻率を下げる原因 になっているのです。
💡 お祝い金とは?
学資保険のお祝い金とは、子どもが特定の年齢(例:小学校入学・中学入学・高校入学など)になると受け取れるお金のことです。
例えば、以下のようなプランがあります。
◆ A社の学資保険プラン(払込総額200万円)
- 6歳(小学校入学) :20万円
- 12歳(中学校入学):30万円
- 15歳(高校入学) :50万円
- 18歳(大学入学) :100万円
このように、分割してお金がもらえるのが「お祝い金付きプラン」です。
❓お祝い金があると返戻率が下がる理由❓
「お祝い金がもらえるなら、お得じゃない?」と思うかもしれませんが、実はお祝い金を受け取ると、受取総額が減ってしまう仕組みになっています。
どういうことかというと、お祝い金を受け取ると、その分の「元本に残るお金」が減るため、運用期間が短くなり、複利効果が薄れてしまうのです。
例えば、同じ200万を支払った場合の返礼率を比較すると、以下のような差が出ます。
◆返戻率の比較(同じ保険料を払った場合)
- お祝い金ありのプラン:返戻率95%(元本割れ)
- お祝い金なしのプラン:返戻率105%(増える)
このように、早く受け取れるお金があるほど、総額で受け取れる金額は少なくなってしまうということです。
お祝い金は本当に必要なのか
「でも、まとまったお金が定期的にもらえるのは便利じゃない?」と思うかもしれません。
確かに、子供の成長に合わせてお金が必要になるタイミングがあります。以下のようなライフイベントにあわせて、まとまったお金が必要となります。
- 小学校入学 → ランドセルや机を購入(10~15万円)
- 中学・高校入学 → 制服・部活の初期費用(5~10万円×2)
- 大学入学 → まとまった資金が必要(100万円以上)
しかし、これらの資金は、「学資保険のお祝い金」でなくても準備できますよね。
ということは!お祝い金狙いなら、自分で貯めた方がいい❓
もし、「お祝い金が欲しいから学資保険に入る」と考えているなら、普通に貯金した方がいい可能性もあります。
一方で、学資保険にどうしても加入したいなら、お祝い金なしで「大学入学時にまとめて受け取るプラン」 の方が、返戻率が高くなりやすいです。
まとめ
「お祝い金プラン」は返戻率を下げる原因になる。
💡学資保険に入るなら、お祝い金なしの方が有利!
3. ほとんどの「学資保険」は元本割れ!?本当にメリットがあるのか?

「学資保険に入れば、将来の教育資金をしっかり準備できる!」と思っていませんか?
しかし、実はほとんどの学資保険は元本割れする可能性がある のです。
💡学資保険の「元本割れ」とは?
「元本割れ」とは、支払った保険料の総額よりも、受け取れる金額が少なくなってしまう状態 のことです。
例えば…
◆ A社の学資保険(返戻率98%)
- 払込総額:200万円
- 受取総額:196万円
👉 4万円のマイナス(元本割れ)
「え!?学資保険って増えるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、貯蓄型の学資保険でも、実は元本割れする可能性があります。
❓なぜ元本割れするのか❓
1️⃣低金利の影響
日本は長年「超低金利時代」が続いており、銀行の定期預金の金利は 0.002% ほど。
その影響で、学資保険の運用も増やすのが難しく、利率が低くなっている のです。
2️⃣保障がついているから
この保険は「貯蓄型」とはいえ、保険の機能がついています。
例えば、「契約者(親)が死亡した場合、以降の保険料が免除され、満期金は満額支払われる」などの保障があります。
これはメリットでもありますが、その分保険会社の負担が増え、返戻率が下がる要因 になっています。
元本割れしない学資保険はあるのか
それでも「学資保険を活用したい!」という場合、元本割れしにくい商品を選ぶことが大切 です。
✅払込期間が短いタイプを選ぶ
👉 一括払いや、10年払込のプランにすると返戻率が上がりやすい
(理由:長期の支払いでは、利率が低くなりやすく、保険会社の運用効率がさがるため)
✅お祝い金なしのプランを選ぶ
👉 お祝い金があると、その分返戻率が下がるので注意
(理由:お祝い金を途中で受け取ると、運用される元本が減り、結果として最終的な受取額が少なくなる)
✅返戻率100%以上の商品を選ぶ
👉 銀行の金利よりは増えるものを選ぶ
(理由:支払った金額よりも受け取る金額が少なくなると、貯蓄としての意味が薄れるため)
ただし、これらの条件を満たしても、必ずしも学資保険がベストな選択肢とは限りません。
まとめ
低金利・保険のコスト・インフレの影響で元本割れすることが多い。
💡返戻率を上げるには「短期払い」「お祝い金なし」を選ぶこと!
4.物価上昇率と金利の関係!学資保険は本当に将来の教育費をカバーできるのか?
学資保険に加入する一番の目的は、「将来の教育費を準備すること」ですよね。
では、今の学資保険の金利や返戻率で、本当に将来の教育費をカバーできるのでしょうか?
ここで大切なのが、「物価上昇率」と「金利」の関係 です。
💡 物価上昇率(インフレ)とは?
物価上昇率とは、モノやサービスの価格が年々上がること を指します。
日本政府は、物価上昇率2%を目標 にして経済政策を進めています。(実際は変動あり)
✅ 2022年の物価上昇率:約3.0%(エネルギー・食品の高騰)
✅ 2023年の物価上昇率:約3.1%(41年ぶりの大きな伸び)
例えば、今100万円で通える大学の学費が、18年後には約170万4800円になるということです。
つまり、子どもが生まれたときに学費として100万想定していた場合、物価上昇を考慮すると約70万分追加で準備しておく必要が出てきます。
⚡このように、今の学資保険で「100万円の満期金」だと、実際の教育費には足りなくなる可能性が高い!
学資保険の金利は❓
この保険は、基本的に銀行の預金よりは金利が高いですが、
最近の低金利時代では、学資保険の金利もかなり低くなっています。
- 学資保険の平均返戻率:105~110%(お祝い金なしの場合)
- 銀行の定期預金金利:0.002%(メガバンクの場合)
- 物価上昇率の目標:2%(実際は2~3%程度)
このように、学資保険の返戻率が105%でも、18年間の物価上昇には追いつかない!結果的に、「教育費を貯めたつもりが実質目減りしていた」という事態に…
❓学資保険は「安全だけど増えにくい」❓
この保険は、「元本保証に近い」「確実に貯まる」という安心感はあります。
でも、インフレの影響で、受け取ったお金の価値が下がってしまう のは避けられません。
⚡学資保険だけに頼ると、インフレの影響を受けてしまう!
だからこそ、「貯蓄+運用」のバランスが大切なんです。
学資保険は「足りない分を補うもの」と考える!
学資保険は「教育費のすべてを賄う」ためではなく、足りない分を補う「保険」の役割 として考えるのがベストです。
- 学資保険だけではインフレに対応できない
- 返戻率が高いプランを選ぶ(お祝い金なし)
- 投資や預金と組み合わせてリスク分散する
まとめ
学資保険ではインフレに対応できないため、将来の教育資金が不足する可能性あり。
💡貯蓄+投資リスクで分散が重要!
5. 学資保険の代わりになる方法は?賢い教育資金の準備方法

学資保険のデメリットを理解したうえで、「じゃあ、学資保険の代わりになる方法ってあるの?」と考える方も多いと思います。実は、学資保険にこだわらなくても、教育資金を効率よく貯める方法はたくさんあるんです!
つみたてNISA
① つみたてNISAで教育資金を増やす 学資保険と違い、つみたてNISAは投資信託を活用した資産運用になります。最大のメリットは、「運用益が非課税」になること!
◆つみたてNISAの特徴
- 年40万円まで非課税で運用(最長20年間)
- 長期運用で複利の効果を活用できる
- 運用リスクはあるが、平均利回り3〜5%程度
例えば、毎月1万円を18年間積み立てた場合、利回りが0%、3%、5%で以下のように増えます。
- 利回り0%(元本のみ) → 216万円回り
- 3%(平均的な運用) → 約280万円
- 利回り5%(好調な運用) → 約340万円
💡つみたてNISAは学資保険よりも大きく増える可能性が高い!
変額保険
② 変額保険で資産を増やす 学資保険と同様に教育資金を準備する方法として「変額保険」も有効です。変額保険は、元本保証はありませんが、運用部分が株式や債券に投資されており、リターンが大きくなる可能性があります。
◆変額保険の特徴
- 保険料の一部が運用される
- 元本保証はないが、リターンは大きい可能性あり
- 長期的に運用し、インフレ対策にも有効
💡変額保険は、リスクを取って高いリターンを得たい場合に適しています。また、インフレに強いという特徴もあります。
ジュニアNISA
③ ジュニアNISA(※2023年末で新規受付終了) ジュニアNISAは、未成年の子ども名義で開設する投資口座です。年間80万円まで非課税で運用できる仕組みでしたが、2023年で新規受付は終了しています。
◆ジュニアNISAの活用方法(既に口座を持っている場合)
- 18歳まで引き出し制限あり(※2024年から制限撤廃)
💡非課税で運用できるので、つみたてNISAよりもメリットが大きいので、学資保険より高いリターンを狙える可能性があります。
財形貯蓄
④ 財形貯蓄(会社員向け) 会社員の方なら、「財形貯蓄制度」を活用できる場合があります。
◆財形貯蓄のメリット
- 財形年金や財形住宅と組み合わせて利用可能
- 会社によっては奨励金(ボーナスのようなもの)がつく場合もある
💡給与天引きで強制的に貯蓄ができるので、自分で貯めるのが苦手な人でも確実に貯蓄ができます。
高金利のネット銀行や定期預金
⑤ 高金利のネット銀行や定期預金を活用 最近では、ネット銀行の定期預金や外貨預金などを利用して、少しでも金利の高いところで貯めるのも一つの手です。
◆普通の銀行預金 vs. 高金利のネット銀行
- メガバンクの定期預金金利:0.002%(ほぼ増えない)
- ネット銀行の定期預金金利:0.2〜0.5%(多少増える)
- 外貨預金(米ドルなど):2.0%前後の金利も可能(為替リスクあり)
💡為替を味方につけて増やすのも一つの手です。
学資保険+預金+投資
⑥ 学資保険+預金+投資で分散するのがベスト! 学資保険だけでなく、「預金・投資・財形貯蓄」などを組み合わせて準備するのが最も賢い方法です。
◆学資保険
元本保証に近い、確実に貯められる
◆変額保険
高リターンを狙いたい場合に適している(元本保証はないがインフレに強い)
◆つみたてNISA
インフレに強く、増やせる可能性が高い
◆財形貯蓄
会社員向け、給与天引きで確実に貯められる
◆ネット銀行の定期預金
安全かつ少し金利が高め
まとめ
学資保険の代わりになる選択肢はたくさんある! 学資保険に加入しなくても、教育資金を準備する方法はたくさんあります。
💡教育プランに合わせて、最適な方法を組み合わせるのがベスト
6. 学資保険は本当に必要?あなたに合った教育資金の選び方
これまでの内容を踏まえると、学資保険にはメリットもデメリットもあり、また、それ以外の教育資金の準備方法もたくさん存在します。
とはいえ、「結局、学資保険には入るべきなのか?それとも、別の方法で準備するべきなのか?」 と迷ってしまう方も少なくあります。
そこで、この章では、学資保険が向いている人・向いていない人を整理しながら、あなたに合った教育資金の準備方法を考えてみます。

📌学資保険が向いている人
- お金を計画的に貯めるのが苦手な人
- 強制的に貯蓄ができる仕組みが欲しいひと
- 親に万が一のことがあった場合に備えたい人
- 銀行預金より少しでも増やしたい人
- 「投資は怖いから、元本が守られる方が安心」と思う人
☢️学資保険が向いていない人
- 少しでも高い利回りでお金を増やしたい人
- インフレリスクを考慮したい人
- 途中解約する可能性がある人
- 自由に資金を使いたい人
「学資保険が絶対に必要!」ではなく、選択肢の一つとして考えることが大切 です。
未来の教育資金をしっかり準備するために、自分に合った最適な方法を選んでいきましょう!
まとめ
学資保険は「向いている人」と「向いていない人」がいる。
💡自分のライフスタイルに合った方法を選ぼう!
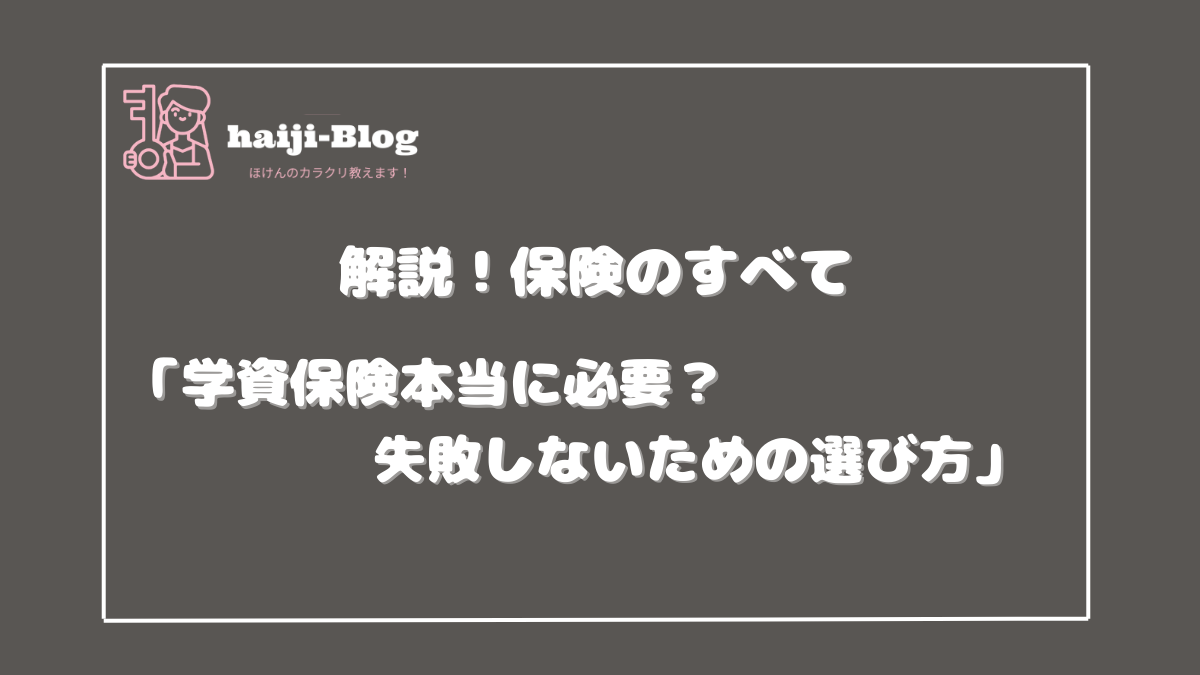





コメント